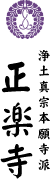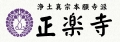M君たちが卒業していった次の年も六年の担任をさせてもらったのですが、
その学級にOちゃんという男の子がいました。
二学期のおしまいの頃です。教室の窓ガラスがちょっと壊れているところから、
冷たい風が吹き込みます。私は紙をまるく切って、壊れたガラスを張りあわせました。
そして、
「これからは特にガラスを壊さんように気をつけるんだぞ。そのためには、窓の近く
で遊ばんこと。わかったか?わかったら手をあげろ!」(先生というものは、よく
手を挙げさせるものですが、あんなことでわかったかわかっていないかを調べたつ
もりでいる先生なんか、たいてい、あまり大した先生ではありません。私もその大し
た先生でない仲間の一人なのですが)子どもたちは、一人残らず挙手してくれました。
それで私は安心して職員室におりていったのですが、次の時間が始まって教室には
いってみると、せっかく私が苦心して張りあわせたガラスを、もうちゃんと壊してし
まっているのです。犯人はOちゃんのようです。私の机の上の糊のびんをもって行って
繕おうとしているのですが、こちらは「思わずかッと」きました。そして、どなり
つけてしまいました。「窓の近くで遊ぶなといったじゃないか。何を聞いていたのか。
お前の耳はどこについているのか?」と、矢つぎ早やにどなりつけておいて、彼の耳
をギューと引っ張ってやりました。でも、それくらいのことでは腹の虫がおさまりま
せん。見ますと、私の糊を無断で使っているものですから、「先生の糊を断りもなしに
使っていらんわい」と言いざま、彼の手の糊をひったくってとりました。
その瞬間、先生ともあろう者が、何という残酷な叱り方をしたのだろうかと思いました。
でも、詫びる気持ちにまではなれません。先生の沽券にかかわりますから・・・・・・。
ところがその翌日です。子どもたちの日記を読み進んでいく中に、Oちゃんの日記帳
にめぐりあいました。
私は、彼の日記を読むのがこわくなってしまいました。私が耳を引っ張ったこと、
糊のびんをひったくって取ったこと、それが書かれているにちがいないからです。
それを書かないくらいの日記なら、書いても書かなくてもどうでもいい日記です。
私は、こわくてなりません。でも読まないわけにはいきません。覚悟をきめて、
恐る恐るノートを開きました。
やはり、Oちゃんは書いていました。が、私を責める文句は一言もないのです。
「ぼくは、きょう、先生が、ぼくたちに寒い目をさせまいと思って辛苦してはって
くださった窓ガラスをこわしてしまいました。ぼくが壊したメゲメゲを、先生がまた、
なおそうとしてくださっているのを見ると、ぼくは、何という悪い子どもだろうかと
思って泣けてきました」
と書いているのですが、私を責めることばは一言も出ていないのです。私を赦して
くれているのです。あのかんしゃくもちの、残酷な私を、赦してくれているのです。
私はもう、はずかしさにいたたまれなくなってしまいました。そして、赤いペンで
「こわそうと思ってこわしたのではなかったのに、そしてまた、自分のこわしたの
を繕おうとしていた君だったのに、あんな叱り方をした先生はいけない先生だった
ね」
と、詫び状を書かずにおれませんでした。
子どもを導かねばならない私が、子どもに導かれて、ここまで来させてもらったのです。