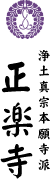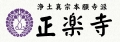大いなるみ親の救いの目あては、この私であったのです。しかし、努めても、努めても、
「死にともない心」を、どうしても超えることができないのです。
浄土真宗のものだけでなく、他宗のものも、キリスト教のものも、「死」の問題にかかわり
のありそうな書物を見つけては、読みあさりました。「死」の問題にかかわりのありそうな
文学作品も、ずいぶん読みあさりました。でも、どんなにしてみても「死にともない心」
を超えることができないのです。
これは、私の真剣さが足りないからだと考えました。朝は、四時起床ということにしました。
そして、起きると、冷たい水で、休中を摩擦して、体中に目を覚まさせ、それから朝の勤行、
勉強・・・・というようにして、毎日をスタートしました。そのことを、別に人に話した
覚えもないのに、同僚の一人が「近頃のあんたには、何か、鬼気のようなものを感じる」
といってくれたこともあります。でも、やっぱり、「死にともない」のです。
何年たっても、何年たってもダメでした。
これは、「死」を、まだまだずっと先のことだと考えているためではないかと、考えました。
それで、父が亡くなった年齢である、六十三歳の十一月三十日を私の最期の日と、心に決めました。
午前四時起床、全身の冷水摩擦、勤行、勉強・・・という毎日を、心に決めた「私の最期の日」
を目指して、何年、年を重ねたことでしょう。でも、どこまでいっても、やっぱり「死にともない」のです。
とうとう、六十三歳になっても、十一月になっても、あせっても、あせっても、というよりは、
あせれば、あせるほど、よけい「死にともない心」が、力を増す気さえするのでした。
そして、どうにもならないまま、十一月三十日を迎えてしまいました。どうにもならないまま、
その日が暮れ、遂に、空しくその時刻を迎えてしまいました。
精も根もつき果てて、如来さまの前に額ずいたまま、頭が上がりませんでした。
ずいぶん、長い間、頭の上がらないまま、額ずき続けていました。
その私に、声が聞こえてくださいました。はっきり、聞こえてくださいました。
それは、『歎異抄』第九のおことばでした。
「念仏申し候へども、踊躍歓喜のこころおろそかに候ふこと、またいそぎ浄土へまゐりたきこころ
の候はぬは、いかにと候ふべきことにて候ふやらん」と、親鸞聖人お尋ねした唯円房さまのお声でした。
ハッとしました。唯円房さまは、後の世に生まれてくる「死にともない私」に代って、「私」のために、
この質問をしてくださったのだと思いました。その質問に対して、親鸞聖人が、「死にともない私」をお叱りに
なるのでなく、「親鸞もこの不審ありつるに、唯円房おなじこころにてありけり」と、「死にともない私」
のためにお答えくださっているのを感じました。親鸞聖人が、高いところからではなく、「私」と同じ
座までおりて、大きくうなずきながらお答えくださるのが何ともいえず、ありがたく思われました。
そして、「よくよく案じみれば、天にをどり地にをどるほどによろこぶべきことを、よろこばぬ」「にて」
「いよいよ往生は一定とおもひたまふなり」「よろこぶべきこころをおさへて、よろこばざるは煩悩の所為なり」
「しかるに仏かねてしろしめして、煩悩具足の凡夫と仰せられたることなれば、他力の悲願はかくのごとし、
われらがためなりけりとしられて、いよいよたのもしくおぼゆるなり」と、答えてくださっているのです。
「われら」の中に、親鸞聖人も、唯円房さまも、「死にともない私」も、含めてくださっているのが、何と
もありがたく思われました。三人で、ご一緒に、「煩悩具足の凡夫」をお目あてに現れてくださった、
真如の月を仰がせていただいているような感動がこみあげてきました。
「死にともない私」のままでよかったのです。「死にともない私」を「殊勝な私」にする必要はなかったのです。
「死にともない私」を「殊勝な私」にする力など、「私」にはなかったのです。そんな力が「私」にあるのだったら、
「他力の本願」などなかったのです。
「なごりおしくおもへども、娑婆の縁尽きて」「ちからなくしてをはるときに」「かの土」へまいらせてもらうのです。
よろこび勇んでではなく、しようことなしに、「いそぎまいりたきこころなきものを」「ことに」「あはれみたまふ」
み仏のところに帰らせていただくのです。「死にざま」をとり繕う必要なんか、微塵もなかったのです。
七転八倒、「死にともない」と、わめきながら終ってもまちがいなく、摂め取っていただける世界が、既に成就されていたのです。