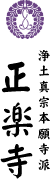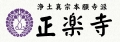中学校の校長を勤めさせていただいていたときでした。あちらこちらでがんばっている卒業生たちが
お正月休みに帰ってきて、学校を会場に同級会をしました。はじめに、自分は今、どんなことを考えながら、
どういうことをがんばっているかという自己紹介をしたのです。
そのときの一人の青年のことばには、みんな感動してしまいました。その青年は申しました。
「ぼくは、中学在学中は、皆さんもご存じのとおり、勉強はできず、わからないことがあっても、
質問もできないだめな生徒でした。勉強ができないから進学はできません。
個人商店に就職したのですが、その店に、ぼくと同年の娘さんがいるのです。
その娘さんが『この靴、磨いといて』と靴磨きをいいつけます。
靴くらいは磨きますが、シャツやズロースの洗濯をさせられたときには、男に生まれて、
同年の娘さんのこんなものまで洗濯しなければならぬかと思うと、無念で、無念で、涙があふれて仕方がありませんでした。
そのとき、涙でかすんだ瞼の向こうに見えてきたのは、但馬の山奥で、貧乏な百姓をやっている両親の姿でした。
それが見えてきたとたん『これくらいのことでくじけてなるか、ズロースだろうが何だろうが洗わせてくれ、
くじけんぞ』という思いがこみあげてきて、ほほえみをとり戻すことができました。皆さん、ぼくの十年先を見ていてください」
というのです。みんなみんな、涙なしには聞くことができませんでした。
さて、人間というものは、この青年のように、「ぼくの十年先をみていてください」
ということにならないと、光を放つことはできないのではないでしょうか。
だめな人間というのは、素質の悪い人間ということではなく、スイッチのはいらない人間ということではないでしょうか。
私は、このように考えて、子どもたちに、いつも、次のように呼びかけてきました。
心のスイッチ
人間の目は ふしぎな目
見ようという心がないと
見ていても 見えない
人間の耳は 不思議な耳
聞こうという心がないと
聞いていても 聞こえない
頭だってそうだ
心が眠っていると頭の働きをしてくれない
まるで 電灯のスイッチみたいだ
仕組みはどんなに立派でも
スイッチを入れなければ
光は放てない